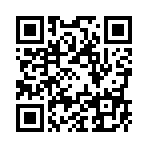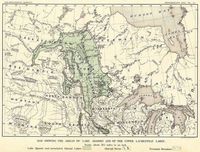2005年07月13日
新生代(8)−第三紀(7)−ゴンフォテリウム

Specimen of Gomphotherium productum at the American Museum of Natural History.
(旧暦 6月 8日)
吉野秀雄忌 相聞歌人吉野秀雄の昭和42年(1967)の忌日
今地球上の陸と海で一番大きな哺乳類として生き残っている鯨目(Cetacea)と長鼻目(Proboscidea)ですが、これらの先祖は約5000万年前の新生代第三紀始新世(Eocene)の中期ころから進化の歴史を始めました。
メリテリウム(Moeritherium trigodon )は、この長鼻目進化の出発点にあるとされている小型種で、体長1.35m、肩高72㎝で、頭骨は長いが鼻はバクに似ていたようです。
1904年、エジプト北部ナイル川左岸のオアシスFayum(ファユーム)の始新世(Eocene)〜漸新世(Oligocene)の地層から発見され、古代エジプトに存在した Moeris 湖の名にちなんで、Moeritheriumと名付けられました。
当時この辺りは河川と湿地で覆われ、カバや海牛のような親水性の生活をしていたと考えられています。
エール大学のFayum探検隊が発見した骨格は、体長2.5mに対して肩高64㎝、腰高70㎝と胴体が異様に長く、海生の海牛類に似ていたとの報告がなされているようです。
新生代第三紀においては、鯨目(Cetacea)と長鼻目(Proboscidea)の祖先は同じではありませんが、どちらも海辺あるいは水辺に生息していたことは、興味深いことです。大きさで、方や海の王者になり、方や陸の王者になったわけですから。
写真のゴンフォテリウム(Gomphotherium)は、アメリカ合衆国ネブラスカ州の約1,200万年前の中新世(Miocene)の地層から発見されました。
現在の長鼻目(アフリカゾウ、インドゾウ)は短い顎が標準ですが、中新世の長鼻目は低く長い顎を持つ種が多かったようで、そのへらの様な顎と牙で、植物を掘るかレーキ(牧草をかき集める大型フォーク)の様に餌をかき集めるのに使ったと考えられています。

Gomphotherium life restoration by Charles R. Knight.
Rodney SteelとAnthony P. Harvey編による「古生物百科事典」(The Encyclopaedia of Prehistoric Life)のゾウ類(Elephants)の解説によれば、「この5,000万年前のうちにゾウ類は体重わずか200㎏からアフリカゾウのような体重約6.5tに33倍の増加をし、表面積は11倍しか増加しなかったため、体の放熱をどう処理するかが大きな問題として残ったが、大きな耳を持つことで解決した」と云うようなことが記述してあります。
それでアフリカゾウなどは耳が大きいんですね。では、「象さんのお鼻はどうして長いのでしょう?」
「母さんが長いから子供も長いってかい?」
「おめー、すったら事言ったってわかんないべや!」
「なまらだ!」
じゃあそれはね、又の機会にお話しませう。
写真のゴンフォテリウム(Gomphotherium)は、アメリカ合衆国ネブラスカ州の約1,200万年前の中新世(Miocene)の地層から発見されました。
現在の長鼻目(アフリカゾウ、インドゾウ)は短い顎が標準ですが、中新世の長鼻目は低く長い顎を持つ種が多かったようで、そのへらの様な顎と牙で、植物を掘るかレーキ(牧草をかき集める大型フォーク)の様に餌をかき集めるのに使ったと考えられています。

Gomphotherium life restoration by Charles R. Knight.
Rodney SteelとAnthony P. Harvey編による「古生物百科事典」(The Encyclopaedia of Prehistoric Life)のゾウ類(Elephants)の解説によれば、「この5,000万年前のうちにゾウ類は体重わずか200㎏からアフリカゾウのような体重約6.5tに33倍の増加をし、表面積は11倍しか増加しなかったため、体の放熱をどう処理するかが大きな問題として残ったが、大きな耳を持つことで解決した」と云うようなことが記述してあります。
それでアフリカゾウなどは耳が大きいんですね。では、「象さんのお鼻はどうして長いのでしょう?」
「母さんが長いから子供も長いってかい?」
「おめー、すったら事言ったってわかんないべや!」
「なまらだ!」
じゃあそれはね、又の機会にお話しませう。
新生代(22)— 新世紀(11)ーザンクレアン大洪水(2)
新生代(21)— 新世紀(10)ーザンクレアン大洪水(1)
新生代(20)−新第三紀(9)−メッシニアン塩分危機
新生代(19)-第四紀(9)-破局噴火
新生代(18)-新第三紀(8)-マンモスの絶滅(2)
新生代(17)-新第三紀(7)-マンモスの絶滅(1)
新生代(21)— 新世紀(10)ーザンクレアン大洪水(1)
新生代(20)−新第三紀(9)−メッシニアン塩分危機
新生代(19)-第四紀(9)-破局噴火
新生代(18)-新第三紀(8)-マンモスの絶滅(2)
新生代(17)-新第三紀(7)-マンモスの絶滅(1)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。