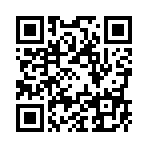2009年12月28日
漢詩(26)-杜牧(2)-阿房宮賦(1)

清 阿房宮圖 袁耀 乾隆四十五年(1780)作 南京博物院蔵
(旧暦 11月13日)
阿房宮賦 杜牧
六王畢、四海一。蜀山兀、阿房出。覆壓三百餘里、隔離天日。驪山北構而西折、直走咸陽。二川溶溶、流入宮牆。五步一樓、十步一閣。廊腰縵迴、簷牙高啄。各抱地勢、鉤心鬭角。盤盤焉、囷囷焉。蜂房水渦、矗不知乎幾千萬落。長橋臥波、未雲何龍。複道行空、不霽何虹。高低冥迷、不知西東。歌臺暖響、春光融融。舞殿冷袖、風雨淒淒。一日之內、一宮之間、而氣候不齊。
六王畢(おわ)りて、四海一なり。蜀山兀(こつ)として、阿房出づ。三百餘里を覆壓(ふうあつ)して、天日を隔離す。驪山 北に構へて西に折れ、直ちに咸陽に走(おもむ)く。二川溶溶として、流れて宮牆に入る。五步に一樓、十步に一閣。廊腰縵く迴りて、簷牙(えんが:軒先に突き出た垂木の端)高く啄(ついば)む。各(おの)おの地勢を抱(いだ)いて、鉤心鬭角(とうかく)せり。盤盤焉(えん)たり、囷囷(きんきん)焉(えん)たり。
蜂房 水渦、矗(ちょく)として幾千萬落なるかを知らず。長橋の波に臥(ぐわ)すは、未だ雲あらざるに何の龍ぞ。複道の空を行くは、霽(は)れざるに何の虹ぞ。高低 冥迷として、西東を知らず。歌臺の暖響は、春光融融たり。舞殿の冷袖は、風雨淒淒たり。一日之內、一宮之間にして、氣候齊(ひと)しからず。
阿房宮(あぼうきゅう)は、秦の始皇帝(Shǐ Huángdì、B.C.259~B.C.210)が始皇26年(B.C.221)に戦国六国の中で最後に残った齊を滅ぼして中国統一を図った後の始皇35年(B.C.212)に、都咸陽の渭水を隔てた南にある庭園、上林苑の中に造営を開始した巨大な宮殿です。
その遺跡は、現在の西安市の西の郊外、阿房宮村一帯に残っています。
三十五年、道を除(はら)ひ、九原より雲陽に抵(いた)る。山を塹(ほ)り谷を堙(うず)め、直に之を通ず。是に於て、始皇以為(おも)へらく、咸陽は人多く、先王之宮廷小なり。吾聞く、周の文王は豐(ほう)に都し、武王は鎬(かう)に都す。豐・鎬之閒は、帝王之都也と。乃ち朝宮を渭南の上林苑中に營作す。先づ前殿を阿房に作る。東西五百步、南北五十丈、上は以て萬人を坐せしむ可く、下は以て五丈の旗を建つ可し。
周馳して閣道を為(つく)り、殿下自り直に南山に抵(いた)る。南山之顚(いただき)を表し以て闕(けつ)と為す。復道を為(つく)り、阿房自り渭を渡り、之を咸陽に屬し、以て天極の閣道の漢(天の川)を絕(わた)り營室(北方玄武七宿の第六宿。距星はペガスス座α星)に抵(いた)るに象(かたど)る。
阿房宮未だ成らず。成らば、更に令名を擇(えら)びて之に名づけんと欲す。宮を阿房に作る。故に天下之を阿房宮と謂ふ。隱宮・徒刑の者七十餘萬人、乃ち分ちて阿房宮を作り、或は麗山を作らしむ。北山の石槨(いしくわく)を發し、乃ち蜀・荊の地の材を寫(うつ)し、皆至る。關中には計るに宮三百、關外には四百餘。是に於て石を東海上の朐界(くかい)の中(うち)に立て、以て秦の東門と為す。因て三萬家を麗邑(りいふ)に、五萬家を雲陽に徙(うつ)し、皆復し、事(つか)はざること十歲。
(史記 秦始皇本紀第六)
始皇35年(B.C.212)、道を開いて、北は九原郡(内蒙古自治区包頭市)から雲陽(陝西省涇陽の北方)に到った。この間、山を削り、谷を埋めて直通させた。
是に於いて始皇帝は思った。
「都の咸陽は人口が多く、先代の荘襄王(B.C.249~B.C. 247)が造営された宮廷では小さすぎる。聞くところでは、周の文王(B.C.1152~B.C.1056)は豐(ほう、西安市西南郊外)に都をつくり、武王(B.C.1087 ?~B.C.1043 ?)は鎬(かう、豐の豐河を隔てた対岸)に都を定めた。かくして豐京と鎬京の間は、一帯がつながって帝王の都となったとのことだ」と。
そこで、群臣が参朝する宮殿を渭水の南の上林苑の中に造営した。まず、前殿を阿房村に作った。東西は500歩(約700m)、南北は50丈(約117m)、殿上には1万人を座らせることができ、殿下には5丈(約11.7m)の旗を立てることができた。
各殿舎を通じる渡り廊下を巡らし、宮殿の下から回廊伝いに南山に到ることができた。その南山の嶺に門を作って表とし、中央の道を挟んで闕(けつ:門観)を置いた。
上下二重の高い廊下を造って阿房村から渭水を渡って咸陽の宮殿に連絡させ、天の中宮である北極星が閣道伝いに天の川を渡って營室星(北方玄武七宿の第六宿。距星はペガスス座α星)に到るのを象った。
しかし、阿房の宮殿はまだ完成しなかった。完成したならば、良い名を選んで命名しようとしたのであるが、宮殿を阿房村に造ったので、天下の人々はこれを阿房宮と云ったのである。
宮刑(陰部を切り取る刑)に処せられた者、および徒刑者70万人余を二手に分けて、一方は阿房宮を造らせ、一方は麗山(りざん)を造らせた。
このために、北山の石を発掘し、蜀や荊の地の木材を輸送させたが、それらは皆到着した。
関中の宮殿は300にのぼり、関外では400余りに達した。かくして、石を東海の朐界(くかい:江蘇省朐県)に建てて秦の東門とした。そして、役夫の労を思い、3万戸を麗邑に、5万戸を雲陽(陝西省涇陽の北方)に移住させて、皆の租税を免除し、徭役(無償の強制労働)に使わないこと10年に及んだ。
さて、この阿房宮賦は、杜牧(803~853)が23~24歳の頃の作で、彼の詩文集である『樊川文集』全20巻の巻頭を飾る名作と評価されています。
杜牧は、古(いにしへ)の始皇帝の失政と驕慢・奢侈を強調する阿房宮の故事を借りて、現皇帝敬宗の行為を風刺したと、友人に心情を吐露しています。
寳暦大起宮室、廣聲色、故作阿房宮賦
樊川文集 巻十六 上知己文章啓 杜牧
寳暦(第16代皇帝敬宗李湛:在位825~826) 大いに宮室を起こし、聲色(音楽や女色)を廣む。故に阿房宮賦を作る。
樊川文集 第16巻 知己に文章を上(たてまつ)るの啓(上申書)
また、この賦(非定型の長篇の韻文で、叙事に適した文体)に感動した時の太学博士呉武陵(?~835)が、科舉の最終試験となる省試の責任者である知貢舉の崔郾(さいえん)に強く推薦したために、杜牧は大和2年(828)、26歳の若さで合格率1~2%の最難関の進士科に合格できたと伝えられています。
崔郾侍郎既拜命、於東都試舉人、三署公卿皆祖於長樂傳舍;冠蓋之盛、罕有加也。時吳武陵任太學博士、策蹇而至。郾聞其來、微訝之、乃離席與言。武陵曰、「侍郎以峻德偉望、為明天子選才俊、武陵敢不薄施塵露。向者、偶見太學生十數輩、揚眉抵掌、讀一卷文書、就而觀之、乃進士杜牧阿房宮賦。若其人、眞王佐才也、侍郎官重、必恐未暇披覽。」於是搢笏郎宣一遍。郾大奇之。武陵曰、「請侍郎與狀頭。」郾曰、「已有人。」曰、「不得已、即第五人。」郾未遑對。武陵曰、「不爾、即請比賦。」郾應聲曰、「敬依所教。」既即席、白諸公曰、「適吳太學以第五人見惠。」或曰、「為誰」曰、「杜牧。」眾中有以牧不拘細行間之者。郾曰、「已許吳君矣。牧雖屠沽、不能易也。」
(唐摭言 卷六 公薦)
崔郾(さいえん)侍郎既に拜命し、東都に舉人(きょじん、進士科を受験する者)を試(ため)す。三署(中書省、門下省、尚書省)の公卿、皆、長樂傳舍に祖(そ:送別の宴を開く)す。冠蓋(冠や覆い)之盛、罕(まれ)に加ふること有る也。時に吳武陵、太學博士に任(あた)り、策蹇(さくけん:駑馬に鞭打つ)して而して至る。郾(えん)、其の來たるを聞くや、微(かす)かに之を訝(いぶ)かり、乃ち席を離れて言を與(あた)う。
武陵曰く、「侍郎、峻德偉望を以て、明天子の為に才俊を選ぶ、武陵敢て塵露を施すこと薄からず。向者(さきに)、偶(たまたま)太學生十數輩に見(まみ)え、眉を揚げ掌(たなごころ)を抵(あ)てて、一卷の文書を讀み、就(すぐ)に之を觀るに、乃(すなは)ち進士杜牧の阿房宮賦なり。若しくは其の人、眞(まこと)に王佐の才(王を補佐する才能)也、侍郎官を重んじ、必ず恐れて未だ暇(いとま)を披覽せず」と。
是に於いて搢笏(しんこつ:高官)郎(次官)一遍を宣(の)ぶ。郾(えん)大(おほ)いに之を奇とす。
武陵曰く、「請う侍郎、狀頭(状元)を與へよ」と。
郾(えん)曰く、「已に人有り」 曰く、「已に得ず、即ち第五の人なり」と。 郾(えん)未だ遑(いそ)ぎ對(こたえ)ず。
武陵曰く、「不爾(しからず)、即(すなはち)賦を比ぶるを請ふ」と。
郾(えん)應聲(おうしゃう:答え述べる)して曰く、「敬依する所を教へよ」と。
既(ことごとく)即席(座席につく)し、諸公白(まう)して曰く、「適(まさ)しく吳太學、以て第五の人に見(まみ)へ惠(めぐ:恩を施す)む」と。 或は曰く、「誰を為す」と。 曰く、「杜牧」と。 眾(衆)中、牧を以て細行(こまかな作法)に拘(こだは)らず間(ひそか)に之(ゆ)く者有り。
郾(えん)曰く、「已に吳君を許す矣(かな)。牧、屠沽(とこ:卑しい者)と雖も、易(か)ふること能(あた)はず」と。
(嘉穂のフーケモン拙訳)
隋の初代皇帝である文帝楊堅(在位581~604)の開皇7年(587)に創設された科挙制度は唐代になっても引き継がれ、特に進士科に及第すると官吏として重んじられ、明經・明法などの他の科よりも高い地位が約束されていました。
そのため倍率も高く、先の『唐摭言』卷一 散序進士には、下記のような記述があります。
其艱難謂之、三十老明經、五十少進士
其の艱難之を謂ふ、三十なれば老いたる明經、五十なれば少(わか)き進士
また、進士科については、『新唐書』卷四十九 志第三十四 選舉志上に次のように記述されています。
進士科起于隋大業中、是時猶試策。高宗朝、劉思立加進士雜文、明經填帖。故為進士者皆誦當代之文、而不通經史、明經者但記帖括。
(新唐書卷四十九 志第三十四 選舉志上)
進士科は隋の大業(605~617)中に起り、是の時は猶ほ策(plan)を試(ため)すのみ。高宗の朝(第3代皇帝高宗李治:在位650~683)、劉思立(考功員外郎)進士に雜文を加へ、明經は帖を塡(みた)す。故に進士と為る者は皆、當代之文を誦(そらん)じ、而して經史に通ぜず、明經の者は但だ帖括を記すのみ。
(嘉穂のフーケモン拙訳)
つづく
杜牧は、古(いにしへ)の始皇帝の失政と驕慢・奢侈を強調する阿房宮の故事を借りて、現皇帝敬宗の行為を風刺したと、友人に心情を吐露しています。
寳暦大起宮室、廣聲色、故作阿房宮賦
樊川文集 巻十六 上知己文章啓 杜牧
寳暦(第16代皇帝敬宗李湛:在位825~826) 大いに宮室を起こし、聲色(音楽や女色)を廣む。故に阿房宮賦を作る。
樊川文集 第16巻 知己に文章を上(たてまつ)るの啓(上申書)
また、この賦(非定型の長篇の韻文で、叙事に適した文体)に感動した時の太学博士呉武陵(?~835)が、科舉の最終試験となる省試の責任者である知貢舉の崔郾(さいえん)に強く推薦したために、杜牧は大和2年(828)、26歳の若さで合格率1~2%の最難関の進士科に合格できたと伝えられています。
崔郾侍郎既拜命、於東都試舉人、三署公卿皆祖於長樂傳舍;冠蓋之盛、罕有加也。時吳武陵任太學博士、策蹇而至。郾聞其來、微訝之、乃離席與言。武陵曰、「侍郎以峻德偉望、為明天子選才俊、武陵敢不薄施塵露。向者、偶見太學生十數輩、揚眉抵掌、讀一卷文書、就而觀之、乃進士杜牧阿房宮賦。若其人、眞王佐才也、侍郎官重、必恐未暇披覽。」於是搢笏郎宣一遍。郾大奇之。武陵曰、「請侍郎與狀頭。」郾曰、「已有人。」曰、「不得已、即第五人。」郾未遑對。武陵曰、「不爾、即請比賦。」郾應聲曰、「敬依所教。」既即席、白諸公曰、「適吳太學以第五人見惠。」或曰、「為誰」曰、「杜牧。」眾中有以牧不拘細行間之者。郾曰、「已許吳君矣。牧雖屠沽、不能易也。」
(唐摭言 卷六 公薦)
崔郾(さいえん)侍郎既に拜命し、東都に舉人(きょじん、進士科を受験する者)を試(ため)す。三署(中書省、門下省、尚書省)の公卿、皆、長樂傳舍に祖(そ:送別の宴を開く)す。冠蓋(冠や覆い)之盛、罕(まれ)に加ふること有る也。時に吳武陵、太學博士に任(あた)り、策蹇(さくけん:駑馬に鞭打つ)して而して至る。郾(えん)、其の來たるを聞くや、微(かす)かに之を訝(いぶ)かり、乃ち席を離れて言を與(あた)う。
武陵曰く、「侍郎、峻德偉望を以て、明天子の為に才俊を選ぶ、武陵敢て塵露を施すこと薄からず。向者(さきに)、偶(たまたま)太學生十數輩に見(まみ)え、眉を揚げ掌(たなごころ)を抵(あ)てて、一卷の文書を讀み、就(すぐ)に之を觀るに、乃(すなは)ち進士杜牧の阿房宮賦なり。若しくは其の人、眞(まこと)に王佐の才(王を補佐する才能)也、侍郎官を重んじ、必ず恐れて未だ暇(いとま)を披覽せず」と。
是に於いて搢笏(しんこつ:高官)郎(次官)一遍を宣(の)ぶ。郾(えん)大(おほ)いに之を奇とす。
武陵曰く、「請う侍郎、狀頭(状元)を與へよ」と。
郾(えん)曰く、「已に人有り」 曰く、「已に得ず、即ち第五の人なり」と。 郾(えん)未だ遑(いそ)ぎ對(こたえ)ず。
武陵曰く、「不爾(しからず)、即(すなはち)賦を比ぶるを請ふ」と。
郾(えん)應聲(おうしゃう:答え述べる)して曰く、「敬依する所を教へよ」と。
既(ことごとく)即席(座席につく)し、諸公白(まう)して曰く、「適(まさ)しく吳太學、以て第五の人に見(まみ)へ惠(めぐ:恩を施す)む」と。 或は曰く、「誰を為す」と。 曰く、「杜牧」と。 眾(衆)中、牧を以て細行(こまかな作法)に拘(こだは)らず間(ひそか)に之(ゆ)く者有り。
郾(えん)曰く、「已に吳君を許す矣(かな)。牧、屠沽(とこ:卑しい者)と雖も、易(か)ふること能(あた)はず」と。
(嘉穂のフーケモン拙訳)
隋の初代皇帝である文帝楊堅(在位581~604)の開皇7年(587)に創設された科挙制度は唐代になっても引き継がれ、特に進士科に及第すると官吏として重んじられ、明經・明法などの他の科よりも高い地位が約束されていました。
そのため倍率も高く、先の『唐摭言』卷一 散序進士には、下記のような記述があります。
其艱難謂之、三十老明經、五十少進士
其の艱難之を謂ふ、三十なれば老いたる明經、五十なれば少(わか)き進士
また、進士科については、『新唐書』卷四十九 志第三十四 選舉志上に次のように記述されています。
進士科起于隋大業中、是時猶試策。高宗朝、劉思立加進士雜文、明經填帖。故為進士者皆誦當代之文、而不通經史、明經者但記帖括。
(新唐書卷四十九 志第三十四 選舉志上)
進士科は隋の大業(605~617)中に起り、是の時は猶ほ策(plan)を試(ため)すのみ。高宗の朝(第3代皇帝高宗李治:在位650~683)、劉思立(考功員外郎)進士に雜文を加へ、明經は帖を塡(みた)す。故に進士と為る者は皆、當代之文を誦(そらん)じ、而して經史に通ぜず、明經の者は但だ帖括を記すのみ。
(嘉穂のフーケモン拙訳)
つづく
漢詩(33)− 曹操(1)- 歩出夏門行
漢詩(32)− 屈原(1)- 懷沙之賦
漢詩(31)−陸游(1)−釵頭鳳
漢詩(30)ー秋瑾(2)ー寶刀歌
漢詩(29)-乃木希典(2)-金州城下作
漢詩(28)ー毛澤東(2)−沁園春 長沙
漢詩(32)− 屈原(1)- 懷沙之賦
漢詩(31)−陸游(1)−釵頭鳳
漢詩(30)ー秋瑾(2)ー寶刀歌
漢詩(29)-乃木希典(2)-金州城下作
漢詩(28)ー毛澤東(2)−沁園春 長沙
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。