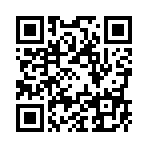2009年02月06日
陶磁器(10)-五彩天馬蓋罐(明/嘉靖窯)

五彩天馬蓋罐(明/嘉靖窯)
(旧暦 1月12日)
句佛忌 本願寺23代法主で伯爵でもあった俳人大谷光演(法名彰如)の昭和18年(1943)の忌日。俳号句佛は、「句を以って佛徳を讃嘆す」の意。明治期の京都画壇の重鎮幸野楳嶺(1844~1895)やその弟子として「楳嶺四天王」の筆頭と呼ばれ、戦前の京都画壇を代表する大家竹内栖鳳(1864~1942)に日本画を学び、優れた日本画を残すなど、多彩な才能を発揮した。
いずこより なれ呼ぶ声を秋のくれ
(信濃川分水路を見て)
禹に勝る 業や心の花盛
嘉靖帝(在位1521~1566)は明朝第12代の皇帝ですが、第11代皇帝の正徳帝(在位1505~1521)には皇子がいなかったために、正徳帝の崩御と共に湖廣安陸州(湖北省鍾祥市)に封じられていた第10代弘治帝( 在位1487~1505)の異母弟の興献王(朱祐杭、1476~1519)の次子(長子は逝去)である朱厚熜(Zhu Houcong)が迎立されて即位し、世宗嘉靖帝となりました。
内閣大学士楊廷和(1459~1529)は、皇位を正当化するために礼部(礼樂・儀式を司る)で検討し、第10代弘治帝を「皇考」、嘉靖帝の実父興献王を「皇叔考興獻大王」、実母を「皇叔母興國大妃」とすることを進言しましたが、嘉靖帝は実父である興献王を「興獻帝」、実母を「興國太后」とすることを強く主張し、南京刑部主事の張璁(1475~1539)および同僚の桂萼(?~1531)等は嘉靖帝の意向を支持して大論争に発展しました。これを世に、「大禮の議」と呼んでいます。
嘉靖3年(1524)7月15日、左順門(現在の北京故宮協和門)に集まって嘉靖帝の方針に不満をとなえた220名の官員は、嘉靖帝の逆鱗に触れて主だった8人が逮捕されてしまいます。
さらにこれを慟哭した従五品員外郎の馬理をはじめとする五品官以下134名が錦衣衛(禁衛軍)の獄に繋がれ、四品官以上86名が停職、7月20日には四品官以上は俸給停止、五品官以下は廷杖(棒打ちの刑)で、その内16名は廷杖が原因で死亡してしまいます。
嘉靖三年(1524)秋七月
戊寅(ぼいん、15日)、廷臣闕(けつ、宮城)に伏(ひれ伏す)して固爭(こそう、つよく諫める)し、員外郎馬理等一百三十四人は錦衣衛(禁衛軍)の獄に下る。癸未(きび、20日)、馬理等廷に杖す、死者十有六人。
明史 巻十七 本紀第十七 世宗一
この後、嘉靖帝はだんだんと政治に意欲を失い、道教を尊崇して長生不老之術を好み、治世後半の27年間は、臣下に謁見したのはたった4回だけだったと伝えられています。
しかし、嘉靖帝が力を注いだのが陶磁器で、景徳鎮に設けた官窯(朝廷専用の窯、嘉靖官窯)に対し、少ない年で1万点、多い年には12万点もの注文を出して陶磁器を作らせました。
嘉靖帝が作らせた瓷器の総数は、記録に残されているものだけで65万9804点もあり、その結果、「大明嘉靖年製」のものが一番多く残っているようです。
明代の瓷器の年号款の特徴は、「永樂款少、宣德款多、成化款肥、弘治款秀、正德款恭、嘉靖款雜」と評されているようですが、大量の注文のために現場では人手が足りず、民間窯の陶工を輪番制で徴発して製作させ、徴発した陶工には一銭の給与も支払われなかったために粗製濫造気味になり、それで「嘉靖款雜」と評されるのでしょうか。
さて、景徳鎮では宦官が監陶官に任じられるのが通例でしたが、嘉靖9年(1530)に至って中央における宦官排斥の動きから、饒州府(江西省鄱陽郡)の佐がその任にあたることになりました。
さらに、御器敞(江西省景徳鎮の珠山に設置された官窯)の充実が図られ、二十三作といわれる分業制度が確立し、窯数は官窯で58座、民窯で20座と伝えられていますが、その後も年々増加の一途をたどり、多いときには官窯が300座、民窯をいれると1,000に近い窯が設けられ、10万人を越える陶工が働いていたと云います。
この嘉靖帝の時代、それまで正統とされた青磁や白磁、あるいは白磁の素地にコバルト系の顔料で文様を描いた後、半透明の白い釉薬をかけて焼成した青花(染付)に代わって、無色透明に近い釉薬をかけて1,200℃くらいで本焼した白い肌の上に、紅、藍、黄、紫、緑、金などを様々な色彩を用いて色々な文様を描き、再び700~800℃で低温焼成した五彩(二色でも六色でも五彩)が登場します。
原料の磁土は純白細緻で乳脂に例えられるほど良質の麻倉土が用いられ、白濁した半透明な釉薬は、祀門石による長石にシダと生石灰を混焼した灰を用いたのではなかろうかと推測されています。
これは、清朝の康煕年間(1661~1722)にジェスイット会の僧侶として布教の名目で2度にわたって景徳鎮を訪れ、瓷器の製造技術をフランスに送ったダントルコールの書翰が参考とされているようです。
ダントルコール著・小林太市郎訳注 『支那陶瓷見聞録』 第一書房 1943
佐藤雅彦補注 『中国陶瓷見聞録』 平凡社東洋文庫363
明代嘉靖窯の五彩の代表作である五彩天馬蓋罐(茶缶)は、高さ15.6cm、口径9.3cm、底径10.9cmで、蓋には6朶の花弁に雲紋が装飾され、肩には枝に纏う花弁、腹部には天馬4頭が紅と黄で描かれ、間は雲紋や波濤で飾られています。
また底には、青花(染付)による楷書で「大明嘉靖年製」の年号款が記されています。
天馬は上帝(天帝)の使いとされ、よい馬を持つことは当時にあっては貴族の地位の象徴でもあったようです。
胴体の部分を上下二つに分けて別々に製作し、それを接合して焼成するという製法は独特のものであり、また、花弁や天馬の描き方も、最初に面を彩り、後から輪郭線を書き入れたもので、伝統的な中国絵画の手法とは全く逆であるとのことです。
嘉靖帝が作らせた瓷器の総数は、記録に残されているものだけで65万9804点もあり、その結果、「大明嘉靖年製」のものが一番多く残っているようです。
明代の瓷器の年号款の特徴は、「永樂款少、宣德款多、成化款肥、弘治款秀、正德款恭、嘉靖款雜」と評されているようですが、大量の注文のために現場では人手が足りず、民間窯の陶工を輪番制で徴発して製作させ、徴発した陶工には一銭の給与も支払われなかったために粗製濫造気味になり、それで「嘉靖款雜」と評されるのでしょうか。
さて、景徳鎮では宦官が監陶官に任じられるのが通例でしたが、嘉靖9年(1530)に至って中央における宦官排斥の動きから、饒州府(江西省鄱陽郡)の佐がその任にあたることになりました。
さらに、御器敞(江西省景徳鎮の珠山に設置された官窯)の充実が図られ、二十三作といわれる分業制度が確立し、窯数は官窯で58座、民窯で20座と伝えられていますが、その後も年々増加の一途をたどり、多いときには官窯が300座、民窯をいれると1,000に近い窯が設けられ、10万人を越える陶工が働いていたと云います。
この嘉靖帝の時代、それまで正統とされた青磁や白磁、あるいは白磁の素地にコバルト系の顔料で文様を描いた後、半透明の白い釉薬をかけて焼成した青花(染付)に代わって、無色透明に近い釉薬をかけて1,200℃くらいで本焼した白い肌の上に、紅、藍、黄、紫、緑、金などを様々な色彩を用いて色々な文様を描き、再び700~800℃で低温焼成した五彩(二色でも六色でも五彩)が登場します。
原料の磁土は純白細緻で乳脂に例えられるほど良質の麻倉土が用いられ、白濁した半透明な釉薬は、祀門石による長石にシダと生石灰を混焼した灰を用いたのではなかろうかと推測されています。
これは、清朝の康煕年間(1661~1722)にジェスイット会の僧侶として布教の名目で2度にわたって景徳鎮を訪れ、瓷器の製造技術をフランスに送ったダントルコールの書翰が参考とされているようです。
ダントルコール著・小林太市郎訳注 『支那陶瓷見聞録』 第一書房 1943
佐藤雅彦補注 『中国陶瓷見聞録』 平凡社東洋文庫363
明代嘉靖窯の五彩の代表作である五彩天馬蓋罐(茶缶)は、高さ15.6cm、口径9.3cm、底径10.9cmで、蓋には6朶の花弁に雲紋が装飾され、肩には枝に纏う花弁、腹部には天馬4頭が紅と黄で描かれ、間は雲紋や波濤で飾られています。
また底には、青花(染付)による楷書で「大明嘉靖年製」の年号款が記されています。
天馬は上帝(天帝)の使いとされ、よい馬を持つことは当時にあっては貴族の地位の象徴でもあったようです。
胴体の部分を上下二つに分けて別々に製作し、それを接合して焼成するという製法は独特のものであり、また、花弁や天馬の描き方も、最初に面を彩り、後から輪郭線を書き入れたもので、伝統的な中国絵画の手法とは全く逆であるとのことです。
陶磁器(14)−琺瑯彩(景徳鎮官窯)
陶磁器(13)−粉彩(景徳鎮官窯)
陶磁器(12)−郎窯紅(景徳鎮官窯)
陶磁器(11)-青瓷盤口鳳耳瓶(南宋/龍泉窯)
陶磁器(9)-成化の鬪彩
陶磁器(8)-青花龍文扁壺(明/永楽窯)
陶磁器(13)−粉彩(景徳鎮官窯)
陶磁器(12)−郎窯紅(景徳鎮官窯)
陶磁器(11)-青瓷盤口鳳耳瓶(南宋/龍泉窯)
陶磁器(9)-成化の鬪彩
陶磁器(8)-青花龍文扁壺(明/永楽窯)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。