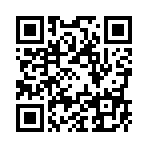2005年02月17日
北東アジア(7)-安禄山(1)

7世紀中頃の唐の勢力範囲
(旧暦 1月 9日)
安吾忌 「白痴」「堕落論」などを著した新潟市出身の作家、坂口安吾の昭和30年(1955)の命日。
中国の唐王朝(618〜907)は、『藩鎮』およびその長官である『節度使』という制度を設けたことにより、その滅亡を早めたと云われています。
唐代の兵制は、当初、律令体制下で農民から徴発された府兵が長安や洛陽の警備と辺境防衛を担っていました。
このうち辺境防衛は、府兵が防人として3年交替で鎮・戌と呼ばれる辺境部隊に勤務していましたが、7世紀になると周辺諸国・諸民族の隆盛によって唐の周辺が圧迫され、防人を基本とする辺境防衛体制が成り立たなくなってきました。
唐の律令体制の根幹を成す均田制・府兵制の両制度の実施には戸籍が必要不可欠でしたが、第6代皇帝玄宗(685〜762)(在位712〜756)の時代になると、窮迫した農民が土地を捨てて逃亡する(逃戸)事が多くなり、また窮迫した農民から土地を買い取る事により、土地の兼併が進んだために戸籍を正確に把握することが難しくなっていました。
ここに均田・租庸調制と府兵制という律令体制は崩壊し、それに代わる新しい税制・兵制が必要となってきました。
新しい兵制は節度使・募兵制と云われ、それまでは人々を労働税として兵役に就かせていましたが、節度使制ではその土地の租税を節度使が徴収し、それを基に兵士を雇い入れて国境防備に使うというものでした。
景雲元年(710)、第5代皇帝睿宗(えいそう)(在位684〜690、在位710〜712)《母・則天武后により即位するが廃立され、武后の死後1代おいて再即位》により河西節度使が最初に置かれると、以後こうした節度使が順次に設置され辺境10節度使の成立をみました。
以下つづく
ここに均田・租庸調制と府兵制という律令体制は崩壊し、それに代わる新しい税制・兵制が必要となってきました。
新しい兵制は節度使・募兵制と云われ、それまでは人々を労働税として兵役に就かせていましたが、節度使制ではその土地の租税を節度使が徴収し、それを基に兵士を雇い入れて国境防備に使うというものでした。
景雲元年(710)、第5代皇帝睿宗(えいそう)(在位684〜690、在位710〜712)《母・則天武后により即位するが廃立され、武后の死後1代おいて再即位》により河西節度使が最初に置かれると、以後こうした節度使が順次に設置され辺境10節度使の成立をみました。
以下つづく
北東アジア(37)-瀟湘八景
北東アジア(36)-中國正史日本傳(2)-後漢書東夷列傳
北東アジア(35)-リットン報告書(3)
北東アジア(34)-リットン報告書(2)
北東アジア(33)-リットン報告書(1)
北東アジア(32)-奉天討胡檄(2)
北東アジア(36)-中國正史日本傳(2)-後漢書東夷列傳
北東アジア(35)-リットン報告書(3)
北東アジア(34)-リットン報告書(2)
北東アジア(33)-リットン報告書(1)
北東アジア(32)-奉天討胡檄(2)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。