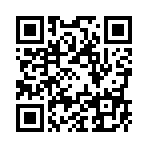2006年01月03日
板橋村あれこれ(15)−加賀藩下屋敷跡

加賀前田家下屋敷築山跡
(旧暦 12月 4日)
板橋村の板橋3、4丁目、加賀1、2丁目一帯は江戸時代、加賀藩前田家の下屋敷があった所です。
前田家の上屋敷跡は有名な東京大学で、東大の代名詞にもなっている赤門(御守殿門)は、文政10年(1827)に11代将軍家斉の第34子(21女)溶姫(やすひめ、1813〜1868)が13代藩主前田斉泰(1811〜1884)に嫁入りしたときに建てられましたが、下屋敷の赤門は、現在も板橋3丁目25番地の真言宗豊山派の寺院如意山観明寺山門として使用されています。
もともとこの門は、下屋敷通用門として旧中山道と国道17号線(新中山道)とが交差している板橋4丁目13番地あたりにあったようですが、明治になって下屋敷跡地が陸軍の火薬製造所(後の東京第二陸軍造兵廠)建設のために接収されたので、一部の建物が観明寺に移築されたもののようです。
ところで我が板橋村のライバル、文京村の東京大学の敷地もかっては下屋敷の時代があったようです。その期間は、3代藩主利常(1594〜1658)が2代将軍秀忠(1579〜1632)から屋敷を拝領した慶長19年(1614)から天和2年(1682)の間でした。
さて我が板橋村の下屋敷は、5代藩主綱紀(1643〜1724)が、延宝7年(1679)、4代将軍家綱(1641〜1680)から6万坪の敷地を板橋宿平尾に賜り、別邸を建てたことに始まります。
そもそも上屋敷、中屋敷、下屋敷といった区分けは、江戸城の天守、本丸等多くの櫓、門を焼失し、大名屋敷500、旗本屋敷770、寺社300、蔵約9,000、橋60、町屋400町、死者10万7,046人といわれている明暦3年(1657)1月18日におきた明暦の大火によりそれまでの拝領屋敷が焼失したため、緊急避難場所或いは緩急時の藩兵の駐屯場所としての屋敷を確保する爲に区分けされたと云われています。
そして、江戸城に一番近い屋敷が上屋敷となり、加賀前田家の場合は、政務を行う表御殿、藩主やその家族の暮らす御本宅や奥御殿、そして藩士が暮らす御貸小屋、その中では、上級藩士の人持小屋、その他の藩士の御貸長屋がありました。また、足軽や小者のための宿舎、火消しのための詰所、土蔵や牢屋、これら建築物を維持管理するための御作事所や大工小屋、馬小屋や飼料所も備えられていました。
一方下屋敷には、藩主の別邸や上屋敷などへ供給するための菜園、藩兵の調練場なども設けられていました。
板橋村の教育委員会の案内板には次のように記載されています。
この付近一帯は江戸時代、加賀前田家の下屋敷跡である。延宝7年(1679)に幕府から6万坪(約19万8000?)を拝領したのに始まり、その後他の下屋敷を返上して天和3年(1683)には合計21万8千坪(約72万1000?)を拝領し、ここを「平尾の下邸」と称した。
文政7年(1824)の「下屋敷御林大綱之絵図」(金沢市立図書館所蔵)には、石神井川を包む広大な敷地に回遊式庭園を設けた屋敷の概要を伝えているが変貌が甚だしく、いまは庭園に築かれた山と思われるこの加賀公園に立つとき、わずかに往時の面影を偲ばせてくれる。
ちなみにこの下屋敷跡は、かの有名な「嘉穂のフーケモン」邸の一部になっています。いやもとい、下屋敷跡のほんの一部が「嘉穂のフーケモン」邸です!
家を建てるときの契約書には、文化財が出土した場合は工期が延長される等の重要事項が記載されていましたが、な〜んにも出てきませんでした。
そして、春には桜が美しい石神井川や下屋敷の回遊式庭園の築山跡と思われる加賀公園は、我が家の裏庭です。ええ、勝手にそう思っています。
石神井川にかかる王子新道の橋は「金沢橋」といい、上流には「加賀橋」や藩主が下向の際に使用した「御成橋」があり、地元の学校には「金沢小学校」、「加賀中学校」があります。
すべて加賀前田家に縁がある土地柄ですが、残念ながら、私「嘉穂のフーケモン」は一度も金沢に行ったことがありません。
「北の都に秋たけて」(時習寮南寮寮歌)で有名な第四高等学校のあった金沢、昭和2年(1927)、第四高等学校理科に入学して柔道部に入り、明けても暮れても道場で寝技の練習に没頭した文豪井上靖先生(1907〜1991)が青春時代を過ごした金沢の地を一度は訪ねてみたいものですの。
一方下屋敷には、藩主の別邸や上屋敷などへ供給するための菜園、藩兵の調練場なども設けられていました。
板橋村の教育委員会の案内板には次のように記載されています。
この付近一帯は江戸時代、加賀前田家の下屋敷跡である。延宝7年(1679)に幕府から6万坪(約19万8000?)を拝領したのに始まり、その後他の下屋敷を返上して天和3年(1683)には合計21万8千坪(約72万1000?)を拝領し、ここを「平尾の下邸」と称した。
文政7年(1824)の「下屋敷御林大綱之絵図」(金沢市立図書館所蔵)には、石神井川を包む広大な敷地に回遊式庭園を設けた屋敷の概要を伝えているが変貌が甚だしく、いまは庭園に築かれた山と思われるこの加賀公園に立つとき、わずかに往時の面影を偲ばせてくれる。
ちなみにこの下屋敷跡は、かの有名な「嘉穂のフーケモン」邸の一部になっています。いやもとい、下屋敷跡のほんの一部が「嘉穂のフーケモン」邸です!
家を建てるときの契約書には、文化財が出土した場合は工期が延長される等の重要事項が記載されていましたが、な〜んにも出てきませんでした。
そして、春には桜が美しい石神井川や下屋敷の回遊式庭園の築山跡と思われる加賀公園は、我が家の裏庭です。ええ、勝手にそう思っています。
石神井川にかかる王子新道の橋は「金沢橋」といい、上流には「加賀橋」や藩主が下向の際に使用した「御成橋」があり、地元の学校には「金沢小学校」、「加賀中学校」があります。
すべて加賀前田家に縁がある土地柄ですが、残念ながら、私「嘉穂のフーケモン」は一度も金沢に行ったことがありません。
「北の都に秋たけて」(時習寮南寮寮歌)で有名な第四高等学校のあった金沢、昭和2年(1927)、第四高等学校理科に入学して柔道部に入り、明けても暮れても道場で寝技の練習に没頭した文豪井上靖先生(1907〜1991)が青春時代を過ごした金沢の地を一度は訪ねてみたいものですの。
板橋村あれこれ(21)-国立極地研究所(1)
板橋村あれこれ(20)-野口研究所
板橋村あれこれ(19)-東上鉄道記念碑
板橋村あれこれ(18)−千川上水(3)
板橋村あれこれ(17)−千川上水(2)
板橋村あれこれ(16)−千川上水(1)
板橋村あれこれ(20)-野口研究所
板橋村あれこれ(19)-東上鉄道記念碑
板橋村あれこれ(18)−千川上水(3)
板橋村あれこれ(17)−千川上水(2)
板橋村あれこれ(16)−千川上水(1)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。